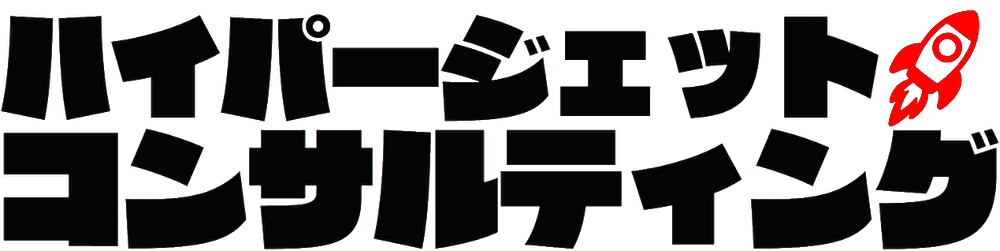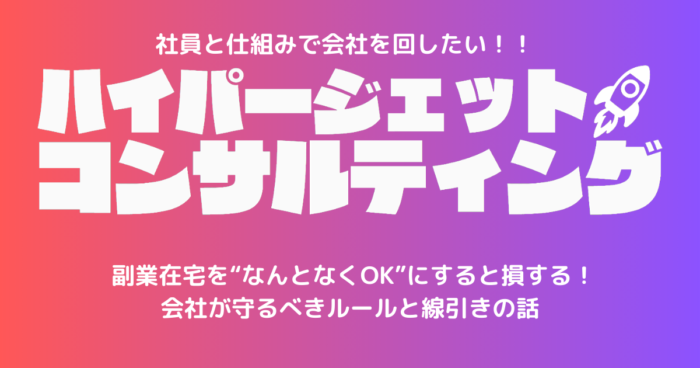なんとなく許してるけど、どこか不安…その違和感の正体
「在宅での副業、別にダメってわけじゃないし…」と、明確な基準を設けずに黙認している企業は意外と多いかもしれません。でも心のどこかで、「これで本当に大丈夫なのか?」という不安を感じている経営者や人事の方も多いはずです。
この違和感の正体は、“何かあったときに責任の所在が曖昧になる”という構造的不安です。社員が副業でトラブルを起こしたとき、会社として関与するべきか、どこまでが本人の責任なのか。その境界線がはっきりしていないと、いざというときに対応が遅れ、企業の信頼に関わる可能性も出てきます。
また、在宅勤務と副業の区別がつきにくくなり、「本当に今、仕事をしているのか」「副業の方に比重が傾いてないか」など、上司側にも無言のストレスが積み重なっていきます。
副業を前提にした働き方が、もはや当たり前になってきた
かつては「副業=本業に対する裏切り」のような空気がありましたが、今はまったく違います。スキルアップや収入補填、ライフワークの実現など、ポジティブな理由から副業に取り組む人が増えています。
とくに在宅で完結できる副業は、クラウドワークスやスキルシェア、ネット販売など、環境さえ整えば誰でも始められる時代になっています。副業の「当たり前化」は、もはや避けようのない社会的流れといえるでしょう。
つまり、企業として問われているのは「副業を許すか否か」ではなく、「副業がある前提で、どうやって企業と社員のバランスを保つか」という問いに変わってきているのです。これは単なる労務管理ではなく、“新しい組織の設計”そのものに関わる課題なのだと思います。
「自由にさせた方がいい」は本当に正しい?ありがちな勘違い
副業について、「社員のやりたいことを尊重したいから、基本的に自由でいいと思っている」という声を聞くことがあります。反対に、「うちはそんな余裕ないから原則NGだ」というスタンスをとる会社もあります。どちらも一見筋が通っているように思えますが、実際にはどちらにも落とし穴があります。
まず、全面的に自由を認めた場合、社員の副業内容や時間配分が把握できず、本業への影響が見えづらくなります。本人はうまく両立しているつもりでも、知らず知らずのうちにパフォーマンスが落ちていたり、体調を崩してしまったりすることも。また、競業避止義務や守秘義務を意識せずに副業を行ってしまうケースもあります。
一方で、厳しくNGを出すと、「どうせ言ってもダメだから隠れてやる」という文化が生まれかねません。これでは、信頼関係どころか、管理も実態把握もできなくなってしまいます。
大切なのは、「自由=放任」ではなく、「ルールのある自由」をどう設計するかという視点。社員の意思を尊重しながら、企業のリスクもきちんと管理する。この両立が、今求められているバランスです。
ルールが曖昧だと、思わぬリスクに巻き込まれる
副業を“とりあえずOK”にしていると、具体的な事例が起きたときに後手に回ることになります。たとえば、ある社員がフリーランスとして他社の案件を受けていたところ、その案件内容が本業の取引先と重なっていた…というようなケース。本人に悪意はなくても、利益相反や信用問題に発展する可能性があります。
また、在宅での業務時間中に副業をしていたり、会社のPCやツールを副業に利用していたりすれば、それは明確なルール違反ですが、ルールがなければ指摘もできません。曖昧な状態を続けることで、結果として社員にも会社にも不利益が生まれやすくなるのです。
さらに、副業の影響で本業の生産性が落ちた場合、評価の基準が揺らぎます。誰かが頑張っていても、「あの人は副業してるから…」といった不公平感が社内に広がれば、組織の一体感も損なわれかねません。
“自由”という言葉に頼りすぎず、会社としての立場を明文化することが、社員を守ることにもつながります。
大切なのは白黒じゃなく、“自社に合った線引き”を決めること
副業をめぐって多くの企業が陥りがちなのが、「OKかNGか」の二択で判断してしまうことです。でも現実はもっと複雑で、白か黒かでは割り切れないケースのほうが圧倒的に多い。だからこそ大事なのは、「自社にとってのリスクはどこにあるのか」「どこまでなら許容できるのか」を丁寧に言語化し、明確な“線引き”をつくることです。
たとえば、以下のようなルールはシンプルかつ効果的です。
- 就業時間内の副業はNG
- 顧客や業務上の機密情報を扱う副業は禁止
- 利益相反となる業種・企業での副業は禁止
- 副業を始める前に内容の申告・確認を必須とする
こうしたルールをもとに、会社として「どこまで認めるか」「何がNGか」を社員と対話することが大切です。ポイントは、“禁止リスト”だけを作るのではなく、“副業を応援する前提”で、健全な運用を支えるガイドラインを設けること。社員の行動を制限するためのルールではなく、安心して副業にチャレンジできる土台づくりとしての制度設計が求められます。
まずは就業規則を見直して、方針を社員に伝えてみよう
いきなり制度化するのが難しいと感じる場合は、まず「就業規則を読み返す」ところから始めましょう。副業に関する規定があるかどうか、あっても時代に合った内容になっているか。特に「在宅勤務」「業務外の活動」などの文言との整合性を確認しておくことが、見直しの第一歩になります。
そして、制度の整備よりも大切なのは「会社として、こう考えている」というスタンスを社員に伝えることです。「副業を応援するけれど、安心して働ける環境を守るために一定のルールは必要です」と、率直な姿勢を言葉にするだけで、社員の納得感は大きく変わります。
制度の完璧さよりも、対話と透明性。会社と社員が同じ方向を向いて、副業というテーマに取り組めるかどうかが、これからの組織運営の分かれ道になるのかもしれません。