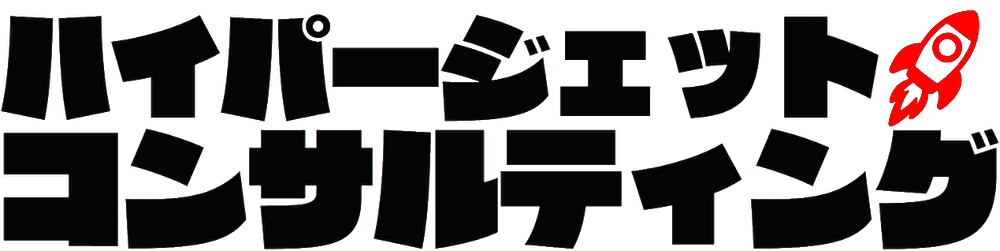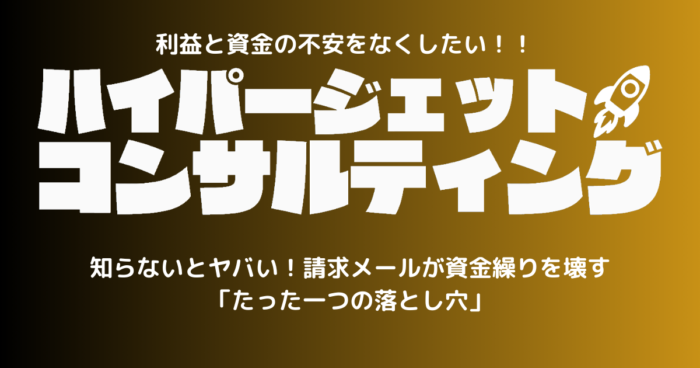支払いの催促って、なんでこんなに気まずいんだろう
支払いのお願いをするメール――文面を打つだけなのに、どうしてこんなに手が止まるんでしょうか。内容はシンプルなはずなのに、「強くなりすぎないかな」「相手に嫌な気持ちをさせたくないな」と、あれこれ考えてしまう。何度も読み直して、結局送るのを後回しにしてしまった…そんな経験、誰しも一度はあるのではないでしょうか。
この“気まずさ”の正体は、たぶんお金にまつわる人間関係の緊張感にあります。お金は感情を動かすもの。相手との関係を壊したくないという気持ちと、でもちゃんと回収しないと困るという現実の板挟みになると、どうしても行動が鈍ってしまう。でも実は、この気まずさを感じている時点で、あなたが相手との関係や会社のことを真剣に考えている証拠でもあるんですよね。
請求対応が人まかせになってると、なぜ回収が遅れるのか
「〇〇さんに任せてるから大丈夫」「たぶんそのうち払ってくれるでしょ」――そんな風に、お金の回収を“人任せ”にしていませんか?個人の判断や感覚に依存した請求業務は、どうしても対応にバラつきが出やすくなります。そしてその“ばらつき”こそが、未回収リスクの入り口なんです。
たとえば、ある担当者はやんわりと一度だけメールを送り、別の担当者は電話で直接催促する。さらに別の人は何日も待ってから動く…。こうした違いがあると、取引先から見ても「この会社の請求はゆるい」と感じられ、支払いの優先順位が下げられてしまいます。実際、「あの会社はきっちりしてるから先に払おう」と思わせる企業ほど、支払い遅延が少ない傾向があります。
つまり、請求対応を属人的にしていると、信頼の低下やキャッシュフローの乱れを招く。お金の流れは“仕組み”で管理しないと、誰かの感覚次第で止まってしまうんです。
言葉遣いよりタイミング?よくある勘違いに注意
請求メールを送るとき、「どう書けば角が立たないか」「失礼にならない言い回しはどれか」と悩む人は多いと思います。もちろん、丁寧な表現や礼儀正しい文章は大切です。でも、実際のところ、文面そのものよりも“いつ送るか”のほうが、支払われるかどうかに直結することが多いんです。
たとえば、支払期日を過ぎてからすぐに軽くリマインドを送るのと、1週間以上経ってから「そろそろ…」と丁寧に催促するのとでは、相手の受け取り方も支払いのスピードも変わってきます。早めに動けば「ちゃんとしてる会社だな」という印象になりますが、遅れると「まあまだ平気か」と感じさせてしまうんですね。
つまり、優先すべきは“文面の完成度”ではなく“反応の早さと一貫性”。適切なタイミングで、適切なテンションで伝えることができれば、強くもならず、遠慮しすぎることもなく、相手も自然と支払いモードに入ってくれます。
たった一通の遅れが、資金繰りを狂わせることもある
「請求メール、もう少し待ってから送ろう」――この“もう少し”が、実は会社の資金繰りに大きな影響を与えることがあります。特に月末や決算前など、キャッシュが動くタイミングでは、一つの入金の遅れが仕入れや給与の支払い、次の投資判断にまで波及することもあります。
中小企業にとっては、数十万円の未回収でも痛手になることがありますし、累積すればあっという間に数百万円規模の資金ショートにつながることもあります。そしてそれは、経営者だけでなく、現場の社員の不安や取引先との信頼関係にも影響を与えかねません。
しかも、請求の遅れが常態化すると、「あの会社は遅れても何も言ってこない」という“ナメられ体質”ができてしまい、遅延が連鎖的に増えていくことも。だからこそ、一件一件の請求が経営全体の健全性に関わる――そう思って取り組む視点が必要なんです。
「うまく伝える」より「仕組みで動く」ほうがラクになる
お金の話はどうしても感情が入りがちで、「相手の気持ちを考えると強く言えない」「丁寧すぎると伝わらないかも」と悩むことが多いですよね。でも、そういうときほど頼りになるのが“個人の気配り”ではなく、“会社としてのルール”です。
たとえば、「支払期日を過ぎたら〇日以内にこの文面でメール」「それでも未入金なら〇日後に電話」など、対応のフローをあらかじめ決めておけば、迷う必要がなくなります。ルールに基づいて動くだけなので、主観が入りづらく、相手にも“個人的な感情”ではなく“会社の方針として対応している”と伝わります。
このように、請求対応を「交渉」ではなく「オペレーション」として設計しておくと、心理的負担もぐっと軽くなります。そして、相手との関係も変にこじれにくくなります。人が頑張って気を使わなくても、お金が回る状態をつくる。これが、長期的に安心して請求できる組織の形なんです。
まずは定型文を作って、チームで回せる体制にしよう
何から始めればいいか分からないときは、とにかく「メールのひな形」を一つ用意するところから始めてみましょう。支払期日を過ぎたタイミングで送るシンプルなテンプレート、それだけでOKです。文面に悩む時間が減るだけでなく、担当者間の温度差も減って、業務がラクになります。
次に、送付のタイミングや手段を軽くまとめて、社内で共有する。たとえば、「期日翌日にリマインド」「3営業日後に再通知」「7日後に電話」など。紙でもチャットでも、簡単なルールを見える化しておけば、それだけで請求業務が“属人化”から“チーム対応”に変わります。
この一歩だけでも、「請求メールが怖い」「言い方に困る」といったモヤモヤはかなり解消されます。そしてそれは、ただ請求がしやすくなるだけでなく、会社全体のお金の流れを安定させる力にもなっていきます。誰かのスキルや勇気に頼らなくても、普通に請求して、普通に回収できる。そんな状態を目指すことが、実は経営の安心を生むんですよね。