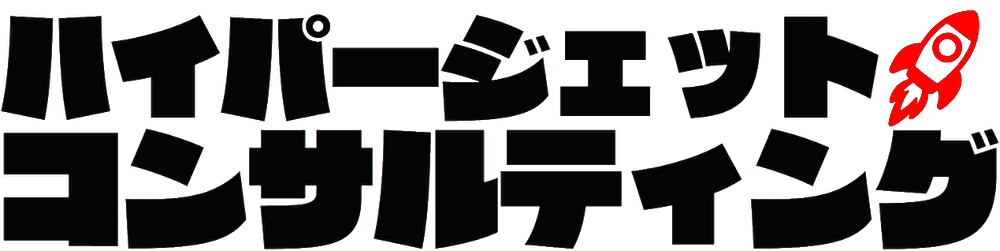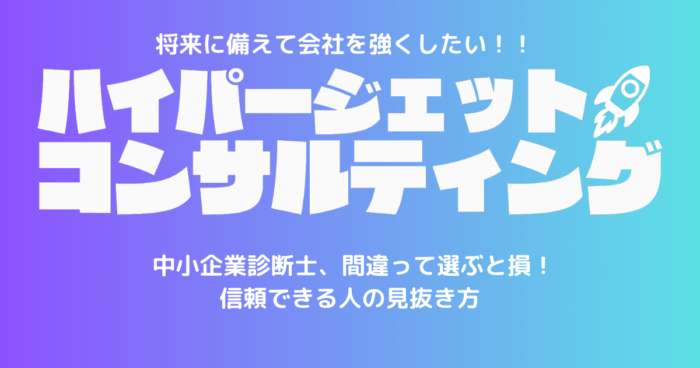紹介されたけど違和感…この人で本当に大丈夫?
「知り合いが良いって言ってたから」「商工会議所で紹介されたから」――そんな流れで会った診断士との打ち合わせ。話してみると、丁寧だし親切ではあるものの、なぜかモヤモヤする。違和感をはっきり言葉にできないまま、なんとなく契約まで進んでしまう…。こんな経験がある方も少なくないと思います。
経営の相談というのは、売上のこと、人のこと、将来のこと――とてもパーソナルで、会社の内側の深い部分に踏み込むテーマが多くなります。だからこそ、「信頼できるか」「腹を割って話せるか」は、想像以上に重要な判断軸です。
相手の人柄や話し方が「心地よい」かどうかは、実は一番わかりやすくて確かなサイン。違和感を見て見ぬふりして始めると、後でやり直すことになってしまうこともあるので、最初の感覚は大切にしてほしいのです。
“診断士=同じ仕事”じゃない時代の背景
ひと昔前まで、「中小企業診断士」といえば、経営計画をつくる、補助金の申請を手伝う、事業の現状を分析して報告書を書く――そんなイメージが一般的でした。でも今は、その枠を超えてさまざまなスタイルの診断士が活躍しています。
たとえば、社長の思考整理に特化している人。現場に入り込んで社員と一緒に改善を回す人。あるいはSNS運用やWEBマーケティングなど、実務領域に強い人もいます。同じ“資格”を持っていても、やっている仕事も関わり方も、まったく違うのが今の現実です。
「診断士なら誰でも同じことができる」という感覚で選んでしまうと、自分が求めていた支援と実際の提供内容が食い違ってしまうこともあります。だからこそ、「この人はどんな関わり方をしてくれるのか?」「うちの課題に合っているか?」を、事前にしっかり確認する必要があります。資格ではなく、“支援のスタンス”で選ぶことが大事な時代です。
実績がすごい人ほど、ズレが生まれることもある
「補助金採択率90%」「年間100社以上支援」など、実績豊富な診断士のプロフィールを見ると、「すごいな、安心できそうだ」と感じるかもしれません。実際、経験があることは大きな強みですし、判断材料にもなります。
でも注意したいのは、その“すごさ”が自社にとって本当に役立つかどうか。たとえば大企業や行政向けの支援実績が豊富でも、自社のような10人未満の現場密着型経営に、どこまで寄り添ってくれるのか――そこには大きなギャップが生まれる可能性があります。
さらに、実績がある診断士ほど、一定の「自分の型」を持っている場合もあります。それがうまくハマればいいのですが、柔軟性がないと、自社の事情に合わない提案をされることも。経験値が高い=万能ではないということを、あらかじめ意識しておくと後悔が減ります。
診断士の選定においては、「この人、何ができる人なのか?」だけでなく、「この人、自分の話をどこまで聞いてくれそうか?」という観点が、とても重要なんです。
合わない相手と続けると、相談がストレスになる
診断士と一度契約してしまうと、「今さら断りにくい」「我慢すればそのうち慣れるかも」といった理由で、なんとなく付き合いが続いてしまうことがあります。しかし、相性の合わない相手と長く付き合うことは、経営者にとって想像以上のストレスです。
「言いたいことがうまく伝わらない」「話をしても納得感がない」「結局、自分の意見を押し通されている気がする」――そんな感覚が積み重なると、相談自体が苦痛になっていきます。結果として、相談の回数が減り、アドバイスを実行する気にもならず、何も前に進まない…という悪循環に陥ってしまいます。
さらに、経営者の態度が変わることで、社員も「また外部の人か…」と警戒してしまい、社内の空気も悪くなることすらあります。そうなると、元を取るどころか、逆に会社の士気を下げる結果にすらなりかねません。
「我慢して使い続ける」のではなく、「違うな」と思ったら早めに見直す。経営という長い道のりの中で、支援者との相性は無視できないポイントです。
話の聞き方で見える「本気で寄り添ってくれる人」
診断士を選ぶとき、「この人、本当にうちのことを考えてくれそうかどうか」は、初回のやり取りで意外と見えてきます。その判断の鍵となるのが、“話の聞き方”です。
たとえば、「今どんな課題があるんですか?」といった表面的な質問だけで終わる人と、「なぜそう感じているんですか?」「これまでどんなことを試されてきたんですか?」と、背景や気持ちまで丁寧に聞いてくれる人とでは、関わり方に大きな差があります。
本気で支援してくれる診断士は、最初から答えを急ぎません。むしろ、経営者自身も気づいていない“思い込み”や“優先順位のズレ”を一緒に整理しようとしてくれます。提案内容の良し悪しよりも、その過程で「この人、ちゃんと聴いてくれるな」と感じられるかが、信頼のベースになるのです。
逆に、「こうした方がいいですよ」「うちが得意なのはこれです」と最初から自分の話ばかりする人は、少し慎重に見た方がいいかもしれません。大事なのは“話す力”より“聞く姿勢”。この違いが、経営者の判断のしやすさを大きく左右します。
迷ったら、まず気になる人と話してみるだけでいい
中小企業診断士を選ぶうえで、いきなり「完璧な相手」を見つけようとすると、なかなか踏み出せません。でも実際は、完璧な人よりも「話してみたら合いそうだった」という“肌感覚”の方がずっと重要です。
そのためにも、迷っているならまずは1回話してみること。無料相談をしている診断士も多いですし、たとえ短時間でも直接会話をすることで、「この人なら一緒に考えていけそうか」が見えてきます。
また、1人だけで決めずに、複数人に会ってみるのもおすすめです。比較することで、自分が何を求めているのか、どんな人に安心感を覚えるのかがより明確になります。
相談すること自体が“前向きな行動”です。完璧な選択でなくてもいい。「まず一歩、誰かに話してみる」――そこから、経営の新しい流れが始まるかもしれません。焦らず、でも止まらず、自分の感覚を信じて進んでいきましょう。