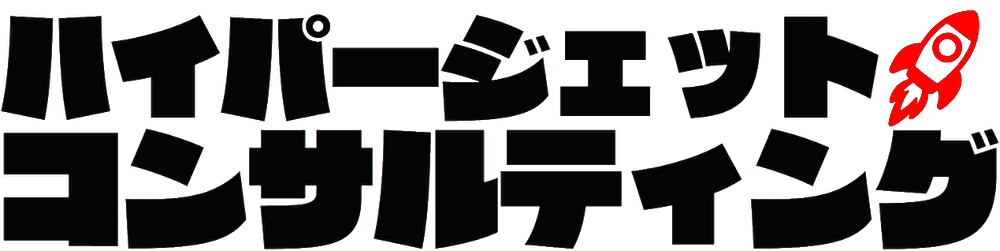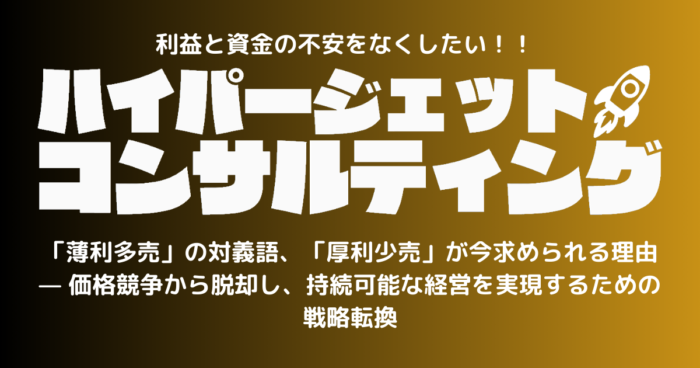利益率の低下に不安を感じる経営者の葛藤
「これ以上値下げできない…でも競合が次々と価格を下げてくる」
このフレーズに心当たりはありませんか?私も中小企業の経営コンサルタントとして多くの経営者から、このような悩みを聞くことが増えてきました。売上は確かに伸びている。しかし、その裏では利益率が年々下がり続けている現実。
ある製造業の社長は私にこう漏らしました。「5年前は30%あった利益率が、今は15%を切っています。売上は1.5倍になったのに、手元に残るお金は減っているんです」
これは「薄利多売」の限界を示す典型的な例です。かつては王道とされた「数を売って利益を確保する」というこのビジネスモデルが、多くの業界で機能しなくなってきているのです。
特に中小企業にとって、この状況は単なる収益の問題ではありません。「このまま続けていけるのだろうか」という将来への不安、「これだけ頑張っているのに報われない」というフラストレーション、さらには「自分の経営判断は間違っていたのか」という自己否定感まで生み出しています。
なぜ今「薄利多売」が行き詰まっているのか
なぜ、長年機能してきた「薄利多売」が今、多くの企業で限界を迎えているのでしょうか。その背景には、ビジネス環境の劇的な変化があります。
まず第一に、インターネットによる価格の透明化が挙げられます。かつては「安い店を探す」ためには、実際に足を運ぶ必要がありました。しかし今や、スマートフォン一つで瞬時に価格比較ができる時代です。消費者は容易に「最安値」を見つけることができ、企業間の価格競争は一層激化しています。
第二に、グローバル競争の本格化です。国内市場だけでなく、海外の低コスト生産者との競争も避けられなくなっています。特に製造業や小売業では、この影響が顕著です。
そして第三に、消費者の価値観の変化があります。「とにかく安ければいい」という消費者層は依然として存在しますが、一方で「価格以外の価値」を重視する層も増えています。環境への配慮、社会的責任、ストーリー性、体験の質など、単純な「安さ」では測れない価値基準が台頭してきているのです。
これらの変化により、多くの産業でコモディティ化(差別化要素の喪失)が進み、価格以外の競争力を持たない企業は苦境に立たされています。「薄利多売」は、コモディティ化した市場では持続可能なモデルではなくなりつつあるのです。
「厚利少売」は単に「値上げして量を減らす」ことではない
では、「薄利多売」の対義語である「厚利少売」に活路を見出せるのでしょうか?
ここで多くの経営者が陥りやすい誤解があります。「厚利少売」を単に「価格を上げて、販売量を減らす」と解釈してしまうことです。
あるアパレル企業の事例を紹介します。この会社は業績不振に陥り、「高付加価値路線」に転換するとして、単純に商品価格を30%引き上げました。結果は惨敗でした。顧客は離れ、売上は激減。結局、半年後には元の価格帯に戻さざるを得なくなりました。
なぜこのような失敗が起きるのでしょうか。それは「厚利少売」の本質を理解していなかったからです。真の「厚利少売」とは、単に価格を上げることではありません。顧客にとっての「価値」を高め、その価値に見合った適正な対価をいただくビジネスモデルなのです。
価値創造なくして価格上昇なし—これが「厚利少売」の鉄則です。
また、「少売」の部分も誤解されがちです。これは「売上を減らす」ことではなく、「特定の顧客層に集中する」という意味合いが強いのです。すべての人に売ろうとするのではなく、自社の価値を最も評価してくれる顧客層にフォーカスするアプローチです。
価値提供型ビジネスモデルへの転換アプローチ
では実際に、どのように「薄利多売」から「厚利少売」へと転換していけばよいのでしょうか。ここでは三つの具体的なアプローチを紹介します。
1. ニッチ市場の開拓
まず考えるべきは、「誰のために存在する企業なのか」という根本的な問いです。大企業のように「すべての人」を対象にするのではなく、特定の顧客層に絞り込む勇気が必要です。
例えば、ある文房具メーカーは、「学生向け低価格文具」という大きな市場での競争に疲弊していました。そこで彼らが選んだのは、「左利きの人向け文具」という小さな、しかし情熱的な顧客層をターゲットにすることでした。左利きの人々の具体的な不便や課題を深く研究し、彼らのためだけに設計された商品を開発。結果として、価格競争に巻き込まれることなく、高い利益率を維持できるようになったのです。
2. 独自性の構築
次に重要なのは、「なぜあなたの会社でなければならないのか」という独自の理由を作ることです。これは必ずしも画期的な技術や特許を持つ必要はありません。むしろ、サービスの提供方法や顧客との関係性構築など、模倣しにくい要素を作り出すことが重要です。
ある町の小さな八百屋さんは、スーパーやネットショップとの価格競争に悩んでいました。彼らが見出した独自性は「地元農家との直接取引と、その生産者のストーリーを伝える」というものでした。各野菜にQRコードを付け、スマホで読み取ると生産者の顔や栽培へのこだわりが見られるようにしたのです。この取り組みにより、「安さ」ではなく「つながり」や「安心」という価値を提供することで、価格競争から脱却することができました。
3. 顧客体験の設計
三つ目は、「商品そのもの」ではなく「商品を取り巻く体験全体」に価値を見出すアプローチです。アップルストアを思い浮かべてみてください。彼らが売っているのは単なる電子機器ではなく、購入前のカウンセリングから、購入後のサポート、コミュニティへの参加までを含めた「体験」なのです。
中小企業でも、この考え方は応用できます。例えば、あるペットショップは単に犬や猫を販売するのではなく、「飼い主になる体験」全体をデザインしました。購入前の相性診断、飼い方教室、定期的な健康相談、飼い主同士の交流会など、「商品+α」の体験価値を提供することで、大手ペットショップチェーンやネット通販との差別化に成功しています。
これらのアプローチに共通するのは、「量」から「質」への転換、そして組織全体での価値提供意識の醸成です。トップだけでなく、現場の一人ひとりが「私たちは何の価値を提供しているのか」を理解し、行動できることが重要なのです。
明日から始める「厚利少売」への転換ステップ
「なるほど、理解はできた。でも明日から何をすればいいのだろう」
多くの経営者がこう感じるのではないでしょうか。大きな転換は一朝一夕にはできませんが、今日からでも始められる第一歩があります。
まず、自社の強みを再定義してみましょう。
紙とペンを用意して、次の質問に正直に答えてみてください。
- 顧客が私たちを選ぶ本当の理由は何か?
- 私たちがなくなったら、誰が最も困るだろうか?
- 私たち自身が最も誇りに思っていることは何か?
これらの問いに対する答えが、あなたの会社の本当の強みであり、「厚利少売」モデルの基盤となります。意外かもしれませんが、この答えは社長一人で出すのではなく、現場のスタッフと一緒に考えることで、より鮮明になることが多いのです。
次に、最も利益率の高い顧客セグメントを特定しましょう。
過去1年間の売上データを見直し、次の分析を行ってみてください。
- どの顧客層が最も利益率が高いか?
- その顧客たちには共通する特徴があるか?
- 彼らが私たちに求めている価値は何か?
多くの場合、全体の20%の顧客が利益の80%を生み出しているという「パレートの法則」が当てはまります。この20%にこそ、あなたの会社の本当のファンがいるのです。
そして、その顧客に対する価値をさらに高める小さな一歩を踏み出しましょう。
例えば、
- 最優良顧客10人に直接電話をかけ、彼らの本音を聞いてみる
- 次回の製品開発に、顧客代表を招いて意見を聞く会を開催する
- 顧客が抱える「本当の課題」を理解するための現場訪問を行う
これらは大げさなことではありません。しかし、この小さな一歩が、「薄利多売」から「厚利少売」への大きな転換の始まりとなるのです。
「安さ」だけでは勝てない時代に、私たちは何を武器にするべきか。その答えは、顧客にとっての「本当の価値」を創造し、提供することにあります。
「薄利多売」から「厚利少売」への転換は、単なるビジネスモデルの変更ではなく、経営哲学の転換でもあります。それは短期的な利益を追うのではなく、持続可能な関係性を構築するための選択なのです。
あなたの会社だけが提供できる価値とは何か—その問いから、新たな経営の扉が開かれるでしょう。