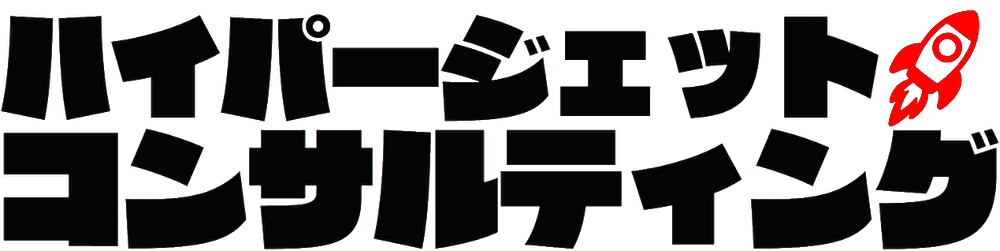なぜ優秀な会社が潰れるのか?
コロナ禍で、15年間取引のあった協力工場が倒産しました。 技術力は一流、品質も申し分ない。なのになぜ?
答えは単純でした。 売上の8割を航空業界に依存し、手元資金は数ヶ月分しかなかった。
この出来事で気づいたのは、多くの中小企業が抱える根本的な問題です:
現場は強いのに、経営戦略で負ける。 技術はあるのに、事業継続で躓く。
そんな中小企業を数多く見てきました。
- そもそも明確な戦略を持っていない
- 日々の受注対応に追われ、将来を考える余裕がない
- 「今まで何とかなってきたから」という経験則頼み
- 危機が起きてから慌てて対策を考え始める
私の答え:「戦略を考える仕組み」をつくる
航空エンジン製造の生産管理に携わってきた私が確信したのは、「戦略策定のスキル不足」ではなく「戦略を考える仕組みの不在」が真の課題だということです。
私のコンサルティングは、エンジンの仕組みになぞらえて設計しています:
- 燃料供給:経営者の想いを具体的な戦略に変換
- 点火:実行可能な形に戦略を分解・設計
- 飛行:継続的な実行を支える仕組みづくり
戦略を描いて終わりではなく、動かせる戦略、飛ばせる仕組みを一緒に創る。 それが私のコンサルティングです。
ここから、なぜ私がこの考えに至ったのか。その経緯をお話しします。
「現場が回る仕組み」を志した原点
「現場を回す」のではなく、「現場が回る仕組みをつくる」
―― これが、私の社会人としての原点でした。
新卒で入社したのは、航空エンジンを製造する重工メーカー。大学院では金属、溶接を研究していた自分が配属を志願したのは、生産管理という”計画”の現場でした。
「全数品質不良だ、急いで現場止めて対策打て!」
「今日中に検査?人足りてないし今日は無理だよ」
「納期変更?できませんよ。お客さんが待ってるんです」
そんなギリギリの現場で、何をどう整えるか。 納期・原価・品質・人――多くの制約条件の中で、最適な戦略を考え、即座に実行する。
正解がないパズルのようなその仕事は、まさに“戦略と現場の接点”でした。
複雑なものづくりの中で学んだ本質はただ一つ。
理論と現実——どちらが欠けてもいい戦略にならない。
理論だけでは現場が動けず、現場感覚だけでは再現性がない。 だから私は、工場を徹底的に分析して現状を把握し、誰よりも理論的に考え戦略を作ることで、計画・工程・発注の仕組みそのものを見直していきました。
その中で、尊敬する先輩に言われた言葉があります。
「この工場にはたくさん問題がある。でもな、”批評家”になるなよ。どうすればうまく回るかを考え続けろ」
批評家とは、できない理由を語る人。 私は、どうすれば動くのか、どうすれば改善できるかを考える人でありたい。 理想論ではなく、制約を抱えた現実の中で考え抜く。
その姿勢こそが、私のコンサルティングの根っこにあります。
現場の戦略から、経営の戦略へ
転機はコロナ禍でした。
航空需要の急激な落ち込みにより、エンジンの生産量も大幅に減少。
その影響で、長年信頼関係を築いてきた協力工場の一つが廃業を余儀なくされました。
廃業した協力工場は、技術力も品質も申し分のない企業でした。 私が生産管理の立場で長年やり取りしてきた中でも、特に信頼できるパートナーの一つ。
しかし、コロナ禍で受注が激減したとき、この企業は致命的な経営判断ミスを犯していました:
- 売上の8割を航空業界に依存していたにも関わらず、リスク分散を怠っていた
- 手元資金が少なく、数ヶ月の売上減で資金ショートに陥った
- 危機が表面化してから慌てて対策を検討したが、既に手遅れだった
この出来事が、私の問題意識を根本的に変えました。
現場の技術力がどれだけ優秀でも、事業ポートフォリオ、財務管理、危機対応といった経営戦略が弱ければ企業は生き残れないという現実を突きつけられたのです。
航空業界の急変を通じて見えてきたのは、多くの中小企業が抱える根本的な課題でした。
そもそも明確な戦略を持っていない。
日々の受注対応に追われ、将来を考える余裕がない。
「今まで何とかなってきたから」という経験則頼み。
危機が起きてから慌てて対策を考え始める。
製造業で培った「仕組み化」の経験から、これらも「経営者の能力不足」ではなく「戦略を考える仕組みがない」問題だと確信しました。
仮説:中小企業の本当の課題は「経営戦略の不在」
この仮説を検証するため、2024年にコンサルティング会社へ転職しました。 経営戦略・補助金活用・業務改革など、幅広いテーマで中小企業の支援に携わる中で、予想を上回る現実に直面しました。
多くの企業で「戦略策定」以前の問題が山積していた。
つまり、「戦略の実行力不足」以前に、「戦略を立てる習慣そのものがない」企業が大半だったのです。
- 「3年後にどうなりたいか」と聞いても明確な答えがない
- 売上目標はあるが、そのための具体的な道筋が描けていない
- 競合他社の動向や市場の変化を把握していない
- 自社の強み・弱みを客観視できていない
コンサルティング会社での経験を通じて確信したのは、中小企業に必要なのは「高度な戦略策定」ではなく「戦略を考え続ける仕組みづくり」だということでした。
多くの企業は、戦略策定のスキルや知識が不足しているのではありません。 戦略を考える時間も、考える習慣も、考える仕組みもないのです。
製造業で身につけた「現場が回る仕組みづくり」のノウハウを、経営戦略を考える仕組みに応用できる。 この独自の強みを活かすため、2025年に独立を決意しました。
「飛ばす支援」の本質
私のコンサルティングは、戦略を描いて終わりではありません。
製造業の生産管理で培った「現場が回る仕組みづくり」の考え方を、経営戦略の実行に応用したものです。
経営戦略は航空エンジンと似ています。
どれだけ精巧に設計されたエンジンでも、点火から推進まで一連のシステムが機能しなければ飛ぶことはできない。
どれだけ立派な戦略を描いても、実際に「飛ばす」仕組みがなければ飛び立つことはできないのです。
1. 燃料供給:経営者の想いを具体的な戦略に変換
生産管理では、営業の受注情報を具体的な製造指示に変換する作業が不可欠でした。
同様に、経営者の「こうなりたい」という想いを、誰でも理解できる戦略に翻訳します。曖昧な目標ではなく、現場が動ける具体性を重視します。
2. 点火:実行可能な形に戦略を分解・設計
複雑なエンジン製造も、工程ごとに分解すれば管理可能になります。
戦略も同じく、実行レベルまで分解し、リソース配分を明確にします。「できない理由」ではなく「どうすればできるか」の視点で設計します。
3. 飛行:継続的な実行を支える仕組みづくり
生産現場では、計画通りに進まないのが当たり前。だからこそ「軌道修正する仕組み」が重要でした。
戦略実行も、進捗確認・課題発見・改善のサイクルを回す仕組みを組み込みます。経営者一人に依存せず、組織として戦略を推進できる体制を構築します。
終わりに
製造業時代に先輩から教わった「批評家になるな」という言葉は、私のコンサルティングの核心です。
多くのコンサルタントは、企業の問題点を指摘し、理想的な解決策を提示します。
しかし現実の中小企業には、人手不足、資金制約、既存業務の負荷など、様々な制約があります。
私は、これらの制約を前提として「それでもどうすれば前に進めるか」を一緒に考えます。
完璧な戦略ではなく、今の状況で実行可能な戦略を。
理論的な正解ではなく、現場で動く解決策を。
15年間の信頼関係があった協力工場の廃業は、私にとって単なる「業界の変化」ではありませんでした。技術力も人間性も申し分ない企業が、経営戦略の実行力不足で消えていく現実を目の当たりにしたのです。
優秀な現場力を持つ中小企業が、戦略実行の仕組み不足で淘汰される。この構造的な問題を変えたい。それが私の「飛ばす支援」の原動力です。
製造業で培った「現場を回す仕組みづくり」の経験を、経営戦略の実行に活かす。
理論と現実の両方を知る立場だからこそできる支援があると信じています。
現場力のある中小企業が、経営力でも勝負できる社会を創る。それが私の使命です。
経歴
- 1995年(平成7年)3月12日生まれ
- 私立広島学院中学校・高等学校卒業
- 大阪大学 工学部 応用理工学科 卒業
- 大阪大学大学院 工学研究科 修了(修士号取得)
資格など
- 中小企業診断士(2025年)
- 基本情報技術者(2020年)
- 工学修士(2019年 “高周波線形摩擦接合法によるステンレス鋼/アルミニウム合金の異材接合”)